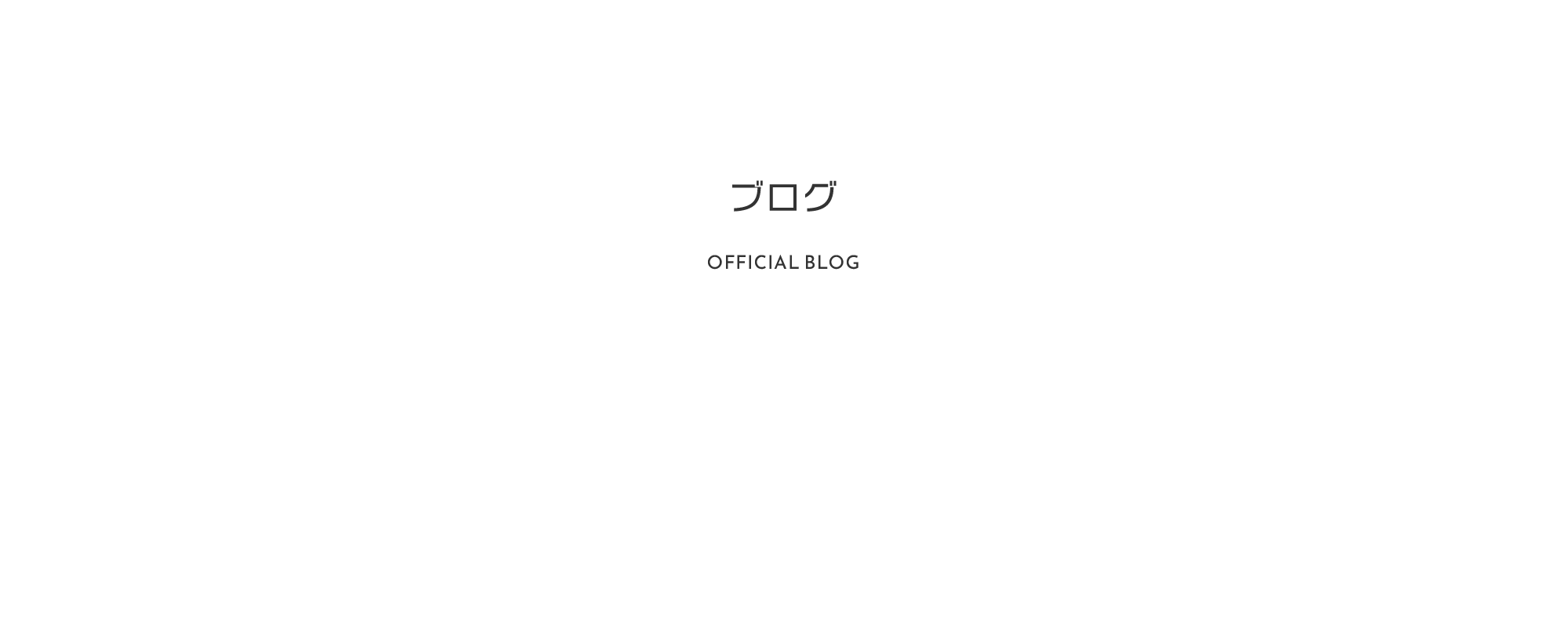今回は、砂地とアスファルトの2種類の地面が混在する敷地での草刈り作業を行いました。
普段の草刈りは「機械を使えば簡単に終わる」と思われがちですが、実際の現場では地面の状態や生えている雑草の種類によって最適な方法が大きく異なります。特に砂地やアスファルトの隙間から生える雑草は、通常の草刈り機だけでは対応が難しいのが現実です。今回は、それぞれの場所に合った道具を選び、効率的かつ丁寧に作業を進めましたので、その様子をご紹介します。
アスファルト面での草刈り
まずはアスファルト面です。
駐車場や通路など、アスファルトの隙間から力強く雑草が伸びているのを見かけたことがある方も多いと思います。硬い地面のわずかな割れ目に根を張り、雨水や風で運ばれてきた土を栄養にして成長するため、非常にしぶといのが特徴です。
そこで今回は、
を使用しました。
草刈りスコップは先端が細くなっており、アスファルトの隙間に差し込んで根を掘り起こすことができます。ノコギリ鎌はギザギザの刃がついているため、硬い茎や根を引っかけて削り取るのに非常に便利です。これらを使うことで、雑草を根元からしっかり取り除き、見た目にもきれいな仕上がりとなりました。
特にアスファルト面は「見た目の印象」に大きく影響します。お客様や訪問者が最初に目にするのは駐車場や玄関周りであることが多いため、清潔感のある環境づくりに直結します。
砂地での草刈り
続いて砂地での作業です。
一見すると草刈り機で一気に刈り取りできそうですが、砂地は柔らかいため、実際にはうまく刈れません。刃が沈み込んでしまい、草を根本から切るどころか、逆に地面をえぐってしまう危険もあります。
そこで今回は、草削りピーラーという専用の手工具を使いました。
ピーラーは地表を薄く削り取るように動かすことで、雑草ごと土の表面を削ぎ落とすことができます。根がしっかり張った雑草も多く苦労しましたが、少しずつ削り進めることで効率的に除草できました。
また、砂地は雨が降ると雑草が生えやすい環境です。そのため、「ただ刈る」だけでなく、根からしっかり除去して発生を抑えることが重要になります。今回のようにピーラーを活用することで、再発の抑制にもつながります。
作業の工夫と安全面
今回の現場は「アスファルト」「砂地」と性質が全く異なる二面がありました。そのため、作業者同士で道具を分担し、効率よく進めることがポイントでした。
また、草刈り作業には飛び石や刃の跳ね返りなどの危険も伴います。特に砂地では小石が混ざっていることが多く、草刈り機を無理に使用すると飛散のリスクが高まります。今回、手工具を中心に行ったのは安全確保の面でも有効でした。
作業を終えて
全体の作業を終えた後、敷地全体が見違えるようにスッキリしました。特に砂地部分は、雑草を削り取ることで広々とした印象に変わり、アスファルト部分は隙間の雑草がなくなることで清潔感が増しました。
作業を見ていたお客様からは、
「こんなにきれいになるとは思わなかった」
「場所に合わせて方法を変えるんですね」
と喜びと驚きの声をいただき、私たちも達成感を感じられました。
草刈りは「場所に合った方法」が大切
今回の作業を通して改めて感じたのは、草刈りはただ刈るだけではなく、地面や環境に合った方法を選ぶことが重要だということです。
「砂地で草刈り機が使えず困っている」
「アスファルトの隙間から草が伸びてきて見栄えが悪い」
そんなお悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。
私たちは、現場の状況を見極めた上で最適な道具を選び、安全に配慮しながら丁寧な作業を行っています。草刈り後の清潔で快適な空間は、お客様にとって日常を気持ちよく過ごす第一歩になります。
今後も「現場ごとに合わせた最適な作業」を心掛け、地域の皆さまに喜んでいただけるよう取り組んでまいります。草刈りや除草でお困りのことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。