-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2025年12月 日 月 火 水 木 金 土 « 11月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
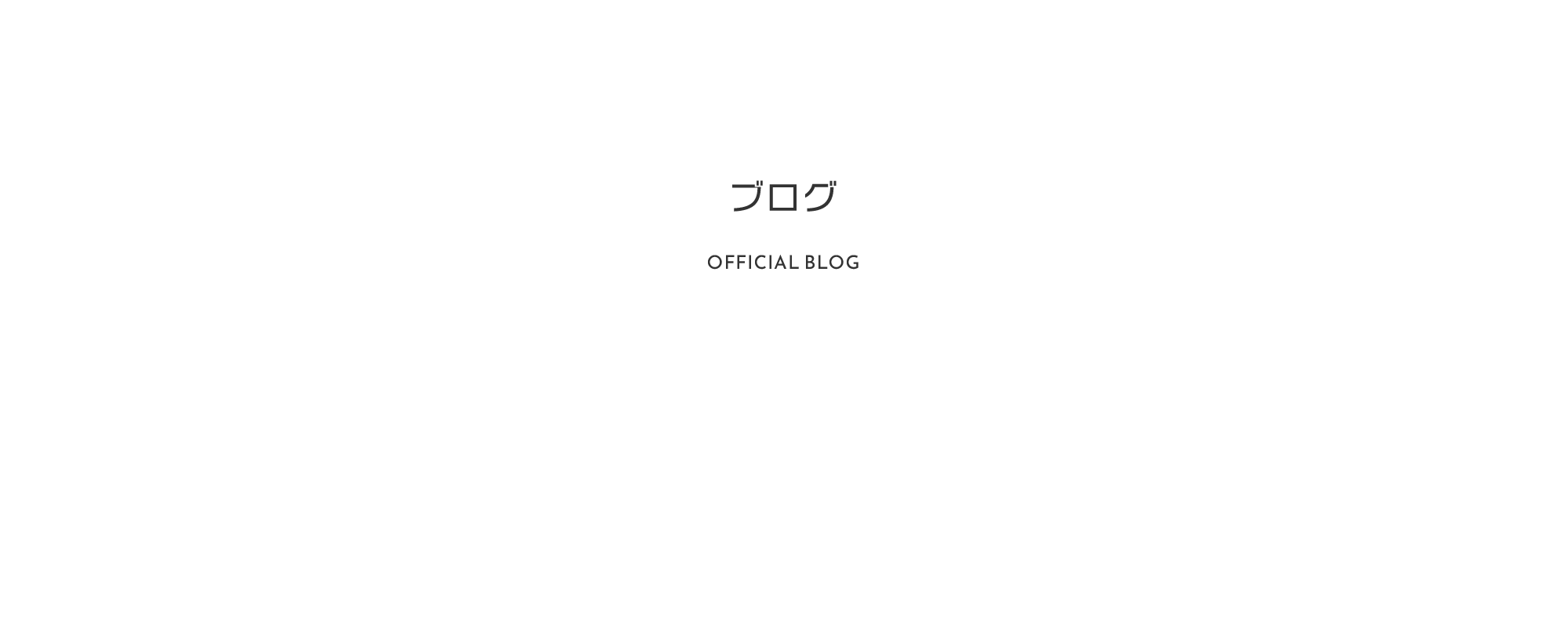
9月23日頃に迎える「秋分の日」。春分の日と同じく、昼と夜の長さがほぼ等しくなる日です。この日を境に日が短くなり、秋の深まりを一層感じられるようになります。夏の暑さが和らぎ、澄んだ空気とともに紅葉や収穫の季節へと移ろう節目の日といえるでしょう。
秋分の日は「祖先をうやまい、亡くなった人々をしのぶ日」として国民の祝日に定められています。古くから日本では、お彼岸の期間にご先祖様へ感謝を伝える習慣があり、秋分の日を中心に前後3日間を合わせた7日間は「秋のお彼岸」と呼ばれます。家族そろってお墓参りをし、仏壇にお供えをして手を合わせる光景は、今も日本各地で大切に受け継がれています。
また、「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉の通り、季節の変わり目を象徴する時期でもあります。夏から秋へ、そしてやがて冬に向かう自然のリズムを、私たちの暮らしの中で感じることができるのです。
秋分の日に欠かせない食べ物といえば「おはぎ」。もち米をあんこで包んだ素朴なお菓子ですが、秋のお彼岸には萩の花にちなみ「おはぎ」と呼ばれます。春は「ぼたもち」と呼ばれることから、季節ごとの呼び名の違いに日本らしい風情を感じます。家族でおはぎを味わいながら、ご先祖様への感謝の心を子どもたちへ伝えるのも大切なひとときです。
さらに、秋分の日は自然を感じる絶好の機会でもあります。田畑では稲刈りが始まり、山や公園では木々の葉が色づき始めます。自然の恵みに感謝しながら、散歩や行楽を楽しむのも良い過ごし方でしょう。現代では忙しさのあまり季節を感じにくい日々を送りがちですが、この日をきっかけに自然とのつながりを意識するのも大切です。
秋分の日は、昼と夜が均衡する特別な日であり、自然と人、過去と未来を結ぶ日でもあります。ご先祖様への感謝を胸に、自然の恵みを楽しみながら、心を穏やかに整える一日にしてみませんか。
