-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2025年8月 日 月 火 水 木 金 土 « 7月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
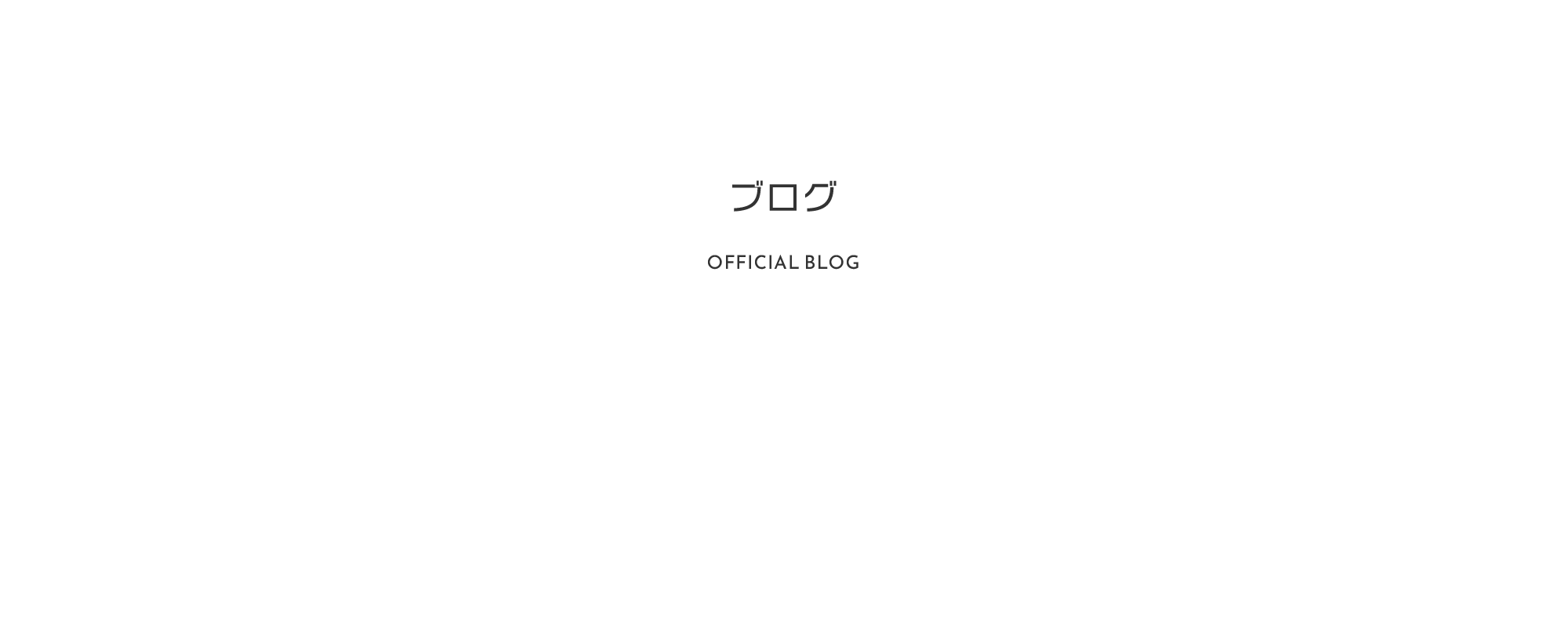

ホテルの客室清掃における心構えは、単に「掃除をする」だけではなく、「お客様にとって気持ちの良い滞在空間を整える」というホスピタリティの一環としての意識が大切です。
目次
自分が宿泊者だったら…という目線で細部まで丁寧に。
髪の毛1本、ゴミ1つにも敏感に気づける観察力が求められます。
見た目のキレイさだけでなく、除菌・消臭など衛生面も大切。
共用のタオル・掃除用具の管理も衛生の一部。
限られた時間の中で、効率よく・でも丁寧に。
チームで協力しながら進める姿勢が必要。
お客様がすでにチェックインしている時間帯や、他のスタッフが働いている時には配慮ある行動を。
制服・身だしなみも「ホテルの一員」として見られていることを意識しましょう。
現場によって求められることが違うこともあります。
新しい清掃手順やお客様対応の変化に対応できる柔軟さと、学び続ける意識が大切です。
清掃スタッフは「ホテルの印象を左右する」重要な役割です。
万屋清掃スタッフでは、ホテル客室清掃の心構え5つを基に、見えない仕事ほどお客様の快適さを支える“縁の下の力持ち”として誇りを持って取り組んでおります。
みなさん、こんにちは!
5月の第2日曜といえば、、そうです母の日です!
5月の第2日曜、今年は5月11日が母の日です。
毎年やってくるとはいえ、つい直前になって「何あげよう…?」と悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。
今回は、予算別&年代別におすすめのプレゼントについてご紹介します(^^)
【予算別プレゼントアイデア】
◆~3,000円:プチギフトで気軽に
・お花(カーネーションは定番ですが、最近はスイーツみたいにアレンジされたものも人気)
・ハンドクリームや入浴剤の詰め合わせ
・おしゃれなエコバッグやキッチン雑貨など、普段使いできるアイテムも◎
◆~5,000円:ちょっと特別な気持ちを込めて
・人気のスイーツセット(地元の名店スイーツなど)
・ネックレスやブレスレットなどのアクセサリー
・アロマディフューザーなど癒しグッズや、少し高級な紅茶セットも喜ばれます。
・母の日限定のフラワーケーキやお取り寄せグルメなど、ちょっとした特別感が演出できます。
◆~10,000円以上:しっかり感謝を伝えたい!
・旅行や温泉のギフトチケット
・ブランドのお財布やバッグ
・高級グルメのカタログギフトなど、日常をちょっと豊かにする贈り物も人気です。
・最近は写真を使ったオリジナルのアルバムや動画を贈る方も増えていますよ♪
【年代別おすすめプレゼント】
・30~40代の母には、実用性とデザイン性を兼ねた家電や美容グッズが人気。
・50~60代には健康志向の食材セットやマッサージクッション、観葉植物などが◎
・70代以降は、趣味に合わせたアイテムや写真入りのオリジナルグッズもおすすめ。使いやすいシンプルなアイテムが喜ばれます。
・また、お花を育てるのが好きな方には、鉢植えのフラワーギフトもおすすめです。
【メッセージを添える】
普段はなかなか言えない「ありがとう」の気持ちを、短くてもいいので手書きで伝えてみませんか?
――――――――――
お母さん、いつもありがとう。
家族のために毎日頑張ってくれて本当に感謝しています。
たまにはゆっくり休んでね。
これからも元気でいてください。
――――――――――
メッセージカードを添えるだけで、気持ちがグッと伝わりやすくなりますよ。贈り物の中身よりも「気持ちがこもっていること」が何より嬉しいというお母さんも多いはず。特に、手書きの一言はとても心に残ります。
また、少し照れくさいという方は、家族写真を添えたり、日頃の出来事を手紙形式でまとめたりするのも良い方法です。時間をかけた分、気持ちがより一層伝わります。
一緒にお出かけするだけでもお母さんは嬉しいのではないでしょうか?
宜しければ当店にいらしてください(´∀`)
素敵な母の日になりますように。
みなさん、こんにちは!
春本番の4月がやってきて、あちこちから桜の便りが届き始めましたね。お弁当を持って花見に行ったり、家族や友人と桜並木を散歩したり、春はイベントがめじろ押しですが、お出かけの際は天気予報もチェックして、急な雨に備えることをお忘れなく~☆
春の風物詩といえばやはり「桜」ですよね!
ということで今回は、桜にまつわる豆知識をご紹介します。せっかく桜を楽しむなら知識をつけて楽しんでいきましょう(^^)/~~~
1.桜前線って何?
桜前線とは、桜(主にソメイヨシノ)の開花日を結んだ線のことです。通常、南から北へと桜の開花が進むため、その様子を天気図の前線のように表したものなんです。気象庁が毎年発表していて、春の訪れを知らせる指標として親しまれています。
桜の開花は気温と深い関係があり、平均気温が約10度を超えるとつぼみが膨らみ始め、約15度になると開花する傾向があるそうです。だから温かい南から順番に咲いていくわけですね。
2.桜の種類はどれくらいあるの?
日本には実はとっても多くの桜の品種があるんです!一般的に知られているソメイヨシノの他にも、八重桜、枝垂れ桜、山桜などが有名ですが、実は日本に自生する野生種だけでも約10種類、園芸品種を含めると約200種類以上もあるんですよ。
ソメイヨシノは江戸時代末期に作られた園芸品種で、実はクローン同士なんです!だから全国どこでもほぼ同じ時期に咲きますが、他の品種は開花時期がバラバラで、早咲きの河津桜から遅咲きの八重桜まで、2月から5月まで長く桜を楽しむことができます。春の楽しみが長続きするのはうれしいですね(^^)
3.桜と花見の歴史は?
日本の花見の歴史は古く、平安時代に貴族の間で梅を愛でる風習があったのが始まりです。その後、鎌倉時代から桜の花見が主流になっていきました。江戸時代には将軍・徳川吉宗が上野公園などに桜を植えさせ、一般庶民にも花見を楽しめる場所を提供したことで、花見が大衆文化として広まりました。
当時は「春を祝う」という意味だけでなく、その年の豊作を祈る農耕儀礼としての意味も持っていたんですよ。花見の席で食べる「花見団子」や「花見酒」の習慣もこの頃から始まったそうです。歴史と共に歩んできた桜と花見、今年の春も大切な人と一緒に楽しみたいですね~ヽ(´▽`)/
いかがでしたでしょうか?
今回は、春本番の4月にぴったりな桜にまつわる豆知識をご紹介しました。桜の美しさをより深く味わえるよう、この知識を持って今年の花見に出かけてみてください。桜の楽しみ方は一つじゃない、ということで、今年の春も家族と、友人と、大切な人と、存分に満喫してくださいね!
春の思い出、たくさん作っていきましょう(^▽^)
私たちにも素敵な思い出をシェアしていただけるととても嬉しいです。
ご来店をお待ちしています!
みなさん、こんにちは!
だんだんと暖かくなってきて、お料理のレパートリーも春モードに切り替わる季節に
なってきましたね。今回は、春ならではの味覚とそのおいしい食べ方についてご紹介
します!
まずは春の定番、菜の花!鮮やかな黄色い花と深い緑の茎は、見た目にも春らしさ満
点です。定番のお浸しはもちろん、パスタや炒め物にも大活躍。特にツナと合わせた
和風パスタは、苦みと塩味のバランスが絶妙なんです。実は菜の花、茹で方がポイン
トなんですよ。塩を多めに入れたお湯で茹でることで、色鮮やかさが保たれ、程よい
歯ごたえに仕上がります。お浸しにする時は、少し濃いめの出汁をかけると苦みが和
らいでより美味しく食べられますよ(*^^*)
菜の花には、ビタミンCやカロテンが豊富に含まれているので、冬の疲れた体にも
ぴったり。特にビタミンCは通常の野菜の2〜3倍も含まれているんです。また、カル
シウムも豊富で、食物繊維もたっぷり。まさに春の健康野菜の代表格と言えますね。
そして、春の味覚の王様と言えば、やっぎりたけのこ!「筍生活」なんて言葉もある
ように、この時期だけの贅沢な食材です。下茹での方法さえマスターすれば、料理の
幅がグンと広がりますよ。実はたけのこの下処理、地域によって方法が違うってご存
知でした?関東では米ぬかを使う方法が一般的ですが、関西では昆布を入れることが
多いんです。どちらも、アクを抜いて柔らかく仕上げるための知恵なんですよ。
若竹煮、たけのこご飯、天ぷら…。どれも春ならではの味わい。最近では、細切り
にして炒め物に使ったり、グラタンの具材にしたりと、和洋中問わず活躍していま
す。特におすすめなのが、たけのこの土佐煮。かつお節の風味とたけのこの食感が絶
妙なハーモニーを奏でます(`・ω・´)ゞ
春キャベツも見逃せない食材の一つ。普通のキャベツと比べて柔らかく、甘みが強い
のが特徴です。巻きが緩く、葉の色も淡い黄緑色をしているのが特徴。このキャベ
ツ、実は栄養価も通常のものより高いんです。ビタミンCはもちろん、胃腸の調子を
整える食物繊維も豊富。シンプルに千切りにして、塩もみだけでも十分美味しい!
豚肉と一緒に蒸し焼きにすると、春キャベツの甘みと豚肉の旨味が絶妙なハーモニー
を奏でます。最近人気なのが、春キャベツのロール白菜風。薄切り肉を巻いて、和風
出汁でコトコト煮込むだけの簡単レシピですが、春キャベツならではの柔らかさと甘
みで、いつもと違った味わいに。
そして、山菜の魅力もお伝えしたいと思います。ふきのとう、こごみ、たらの
芽…。それぞれ独特の香りと食感があって、天ぷらや和え物にぴったり。特にふき
のとうは、春の訪れを告げる香りの代表格。苦みの中にある独特の芳香は、まさに春
そのもの。天ぷらにすると香りが際立ち、日本酒のおつまみにも最高です。
山菜採りを趣味にしている方も多いですよね。ただし、素人判断は禁物。必ず経験者
に同行するか、確実に判断できるものだけを採るようにしましょう。最近では、栽培
された山菜も多く出回っているので、安心して楽しむことができます。
春野菜は、冬の間に体に溜まった余分なものを排出する効果もあるんです。山菜類に
含まれる苦味成分には、消化を促進する働きがあり、まさに「春の目覚め」を助けて
くれる食材なんですよ。自然の恵みって、本当に素晴らしいですね(*^-^*)
さあ、みなさんも春の味覚を探しに、市場やスーパーに出かけてみませんか?きっ
と、新しい発見や楽しみ方が見つかるはずです!
みなさん、こんにちは!
寒い日が続きますが、実はこの季節だからこその美味しい食材がたくさんあるんです。今回は、2月の旬の味覚についてご紹介します(^^♪
まずは、寒締めほうれん草から。寒締めって何だろう?と思われる方も多いかもしれませんね。これは、寒さを利用して甘みを増した野菜のこと。ほうれん草は寒さにあたることで、凍らないように体内に糖分を蓄えるんです。その結果、甘みが増して、より美味しくなるんですよ。
お浸しにすると、普通のほうれん草との違いがよく分かります。生食でも甘みが感じられ、サラダに入れても美味。また、凍らせて作る「凍み(しみ)」も、独特の食感と旨味が楽しめる伝統的な保存食です(*^^*)
次は、冬の味覚の王様、カキ(牡蠣)。寒い時期のカキが特に美味しいのは、産卵期を前に栄養を蓄えているから。ぷりぷりした身は、ミネラルたっぷりで栄養価も抜群です。
カキの調理法は実に様々。定番の生食はもちろん、蒸し牡蠣、牡蠣フライ、牡蠣鍋と、どれも絶品。最近は、オイル漬けやスモークなど、おしゃれな加工品も人気です。生食の際は、食中毒予防のため、必ず信頼できるお店で購入しましょう。
フグも、2月が旬。毒を持つ魚として知られていますが、専門の調理師さんが安全に処理したフグは、透明感のある味わいが特徴。薄造りにすると、歯ごたえと旨味が絶妙です。てっちり(フグ鍋)は、コラーゲンたっぷりのお出汁が体を温めてくれます。
寒ブリも見逃せない冬の味覚。寒い時期の脂ののりは格別。刺身はもちろん、ブリ大根も絶品です。脂が乗っているからこそ、大根おろしや薬味との相性が抜群なんです。
その他にも、真ガレイ、メバル、ワカサギなど、冬の魚は脂がのっていて美味しいものばかり。特にワカサギは、天ぷらや唐揚げにすると、カラッと香ばしく、小骨まで美味しくいただけます(^ω^)
野菜では、春菊や九条ネギも今が旬。寒さで甘みを増した野菜は、お鍋やすき焼きの具材として最高。また、寒い時期に収穫される菜の花は、苦みが少なく、春の訪れを感じさせる香りが特徴です。
旬の食材は、その季節に一番栄養価が高く、美味しく、そして経済的。ぜひ、この時期ならではの味覚を、ご家庭でも楽しんでみてください。温かいお鍋や、こだわりの刺身、seasonal(季節限定)な食材を使った料理で、寒い冬を乗り切りましょう!
各食材の調理の際のポイントもご紹介しますね。
寒締めほうれん草は、お浸しにする時は熱湯でさっと茹で、すぐに冷水にさらすのがコツ。水気をしっかり絞って、だし醤油やごま油でさっと和えるだけで、甘みと風味が際立ちます。
カキは、生食用なら、まずしっかり洗って殻付きのままグリルで焼くのがおすすめ。口が開いたら食べ頃です。ポン酢やモミジおろしを添えて。加熱用なら、フライパンでソテーして、お好みでクリームソースや、オイスターソースで味付けを。
フグは、てっちりにする時は、アラと身を分けて調理するのがポイント。終盤に白子を入れると、とろけるような濃厚さが楽しめます。薬味は、もみじおろしと青ネギを添えて。
寒ブリは、刺身で食べる時は、5分程度氷水に漬けてから切り分けると、身が引き締まっておいしくなります。ブリ大根は、ブリを軽く焼いてから煮ると、臭みが消えて上品な味わいに。
冬の味覚は、丁寧に下ごしらえして、素材の味を活かすのが一番。旬の美味しさを存分に楽しんでくださいね(^o^)丿
この冬に食べた美味しいものを私たちにも教えてください。精一杯のおもてなしをご用意してお待ちしています。
お会いできるのを楽しみにしています!
みなさん、こんにちは!
新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いしますね(^o^)丿
年が明けると、さまざまな伝統行事が待っていますよね。どれも由緒ある行事なので
すが、ただ何となく参加しているという方も多いのではないでしょうか?そこで今回
は、お正月の伝統行事について、その意味や由来をご紹介していきます!
まずは、初詣からスタート!初詣は、その年の無事と幸せを願って神様にご挨拶に行
く大切な行事です。多くの方が元日に行かれると思いますが、実は1月1日〜1月7日ま
でが松の内と呼ばれる期間。この間であれば、いつ行っても「初詣」になるんです
よ。混雑を避けて、2日以降に行くのもおすすめです。
初詣の参拝方法も、きちんと押さえておきたいポイントです。鳥居をくぐる前に一
礼、参道は端を歩き、中央は神様の通り道。手水舎での清め方は、左手で柄杓を持
ち、右手を清め、次に右手で柄杓を持ち直して左手を清めます。その後、左手に水を
受けて口を清め(飲んだ水は飲み込まず脇に吐き出します)、最後に柄杓を立てて柄
を清めます。
次は初日の出!新年を告げる朝日を拝むことには、太陽神である天照大御神を敬う意
味が込められています。最近では、初日の出クルーズやスカイツリーなどの展望台で
の観賞も人気ですね。ご自宅のベランダや近所の高台でも、ゆっくり朝日を拝むこと
ができますよ。気象庁のウェブサイトで日の出時刻を確認して、少し早めに目的地に
到着するのがおすすめです(*^^*)
そしてお待ちかねのおせち料理!黒豆は「まめに暮らせますように」、数の子は「子
孫繁栄」など、一つ一つの料理に縁起の良い意味が込められています。田作りは五穀
豊穣、昆布巻きは「喜び」を表すなど、実は知らない意味がたくさん。最近では、和
洋折衷のおせちや、一人用のミニおせち、オードブル形式のパーティーおせちなど、
ライフスタイルに合わせた楽しみ方も増えてきましたね。
伝統的なおせちを全て手作りするのは大変ですが、一品だけでも作ってみるのはいか
がでしょうか?黒豆や煮しめなど、基本の作り方を覚えておくと、普段のお料理の幅
も広がりますよ。
最後は1月7日の七草粥です。お正月のごちそうで疲れた胃腸を休めるという実用的な
意味と、春の七草を食べて無病息災を願う意味があります。七草は「せり、なずな、
ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ」。スーパーでも七草セットが
売られているので、ぜひチャレンジしてみてくださいね!七草粥を食べながら、「唐
土の鳥が日本の正月に、渡らぬ先に、七草なずな」と唱えるのも粋な楽しみ方です
(^−^)
お正月の伝統行事には、先人たちの知恵と願いが詰まっています。形を変えながら
も、大切に受け継がれてきた行事を、現代の暮らしに合わせて楽しんでいきましょ
う!
お正月の行事を楽しんだ後は、気持ちを新たにこれからの1年の過ごし方に想いを馳
せてみてはいかがでしょうか。そのために私たちは快適な時間を提供できればと思い
ます。
良い計画を思いついたら私たちにも教えてください!お会いできるのを楽しみにして
います^^
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
みなさん、こんにちは!
12月になると、日本中が慌ただしい雰囲気に包まれますね。「師走」と呼ばれるこの
時期は、一年の締めくくりを告げる、とても特別な月です。師走の伝統と慣習につい
て、今回はお話ししていきたいと思います(^^)/~~~
?「師走」の由来と意味
「師走」という言葉、その由来をご存知でしょうか?もともとは、僧侶(師)が年末
の法要の準備に走り回っていたことから生まれた言葉とされています。一年で最も慌
ただしい月、駆け回る様子を表現した奥深い言葉なんです。
現代では、年末の慌ただしさを象徴する言葉として広く使われています。仕事の締め
くくり、年賀状の準備、年末年始の準備など、実に多くのことが同時進行する月。ま
さに走り回らなければならない、そんな月なのです(´ω`)
?忘年会文化と職場の絆
師走の風物詩といえば、なんといっても「忘年会」。一年の労をねぎらい、同僚や仲
間との絆を深める大切な機会です。古くは江戸時代から続く日本独自の風習で、現代
では企業文化の重要な要素となっています。
お酒を交わしながら、一年の出来事を振り返り、来年への抱負を語り合う。普段は言
えないような感謝の言葉を伝え合える、とても貴重な時間なんです。
?大掃除の意味と精神性
師走の伝統行事といえば、「大掃除」も外せません。これは単なる掃除ではなく、一
年の汚れや穢れを落とし、新しい年を清らかに迎えるための精神的な儀式でもありま
す。
家族全員で家中を隅々まで掃除し、新しい年への準備を整える。この行為には、単な
る衛生管理以上の深い意味が込められているのです。
?年越しそばと家族の絆
大晦日の夜に欠かせないのが「年越しそば」。長く伸びる麺は、長寿や縁の切れるこ
とのない幸せを象徴しています。年の瀬に家族や大切な人と一緒に食べることで、来
年への希望と絆を確かめ合うんです。
?初詣の準備と新年への期待
師走の終わりには、初詣の準備も始まります。新しい年の幸せと健康を祈願する、日
本の伝統的な行事。初詣の準備と並行して、お正月の準備も進みます。鏡餅を飾り、
おせち料理の準備を始める家庭も多いでしょう。
いかがでしたでしょうか?
師走は、一年を締めくくり、新しい年への希望をつなぐ、とても特別な月なんです。
慌ただしさの中にも、深い伝統と文化、そして家族や仲間との絆を感じられる、素晴
らしい季節です。今年最後の月を、日本の伝統と共に、心豊かに過ごしてください
ね。
現在一緒に働く仲間を募集中です!来年はあなたとも、充実した1年を過ごせたこと
を語り合えることを楽しみにしています。お気軽にお問い合わせください。
新しい年への希望を胸に、素敵な師走をお過ごしください!
みなさん、こんにちは。
秋も深まり、森や山々が赤や黄色に染まり始めましたね。そんな秋の訪れを感じられ
るのが、何と言っても美味しい季節の食材を味わうこと!今回は、11月に旬を迎える
食材をご紹介したいと思います(`・ω・´)ゞ
□■ 松茸 – 秋の贅沢♪ ■□
秋の風物詩の代表選手と言えば、この「松茸」ですね。深い森の中で育つこの珍しい
食材は、まさに秋の贅沢。独特の芳香と、柔らかい食感が魅力です。
松茸は、主に10月上旬から11月にかけて収穫期を迎えます。産地では丁寧に手摘みさ
れ、新鮮なうちに市場に出回ります。その味わいは格別で、炭火焼きや土瓶蒸し、天
ぷらなどで楽しめます。贅沢な逸品ですが、秋ならではの味覚を存分に堪能できるで
しょう。
□■ サンマ – 秋刀魚の美味しさ ■□
秋の味覚と言えば、抜群の脂ののったサンマ(秋刀魚)も外せません。脂がのりに乗
り、焼いたときの香ばしさが堪らない逸品です。
サンマの旬は10月頃から11月にかけて。北海道や三陸沖で獲れたての新鮮なサンマ
は、塩焼きや干物、煮付けなど、様々な調理法で楽しめます。特に、身がプリプリで
脂がのったサンマを塩焼きにすると、身がふっくらとした食感と、口の中でとろける
ような味わいが堪能できます。
こうしたサンマを秋の夜長に頬張るのは、とても贅沢な気分を味わえるはずです。
□■ 栗 – 心も体も温まる ■□
秋の味覚の定番といえば、やはり「栗」ですね。栗は10月中旬から11月にかけが旬を
迎えます。
栗は、焼き栗や栗ご飯、渋皮煮など、さまざまな調理法で愉しめる食材。香ばしさと
甘みが特徴で、体も心も温まる味わいです。
中でも、炉端で焼いた栗は格別。外はパリッと香ばしく、中はホクホクとした食感が
堪能できます。お酒のおつまみにもぴったりですね。
また、栗は旬の時期にしか味わえない食材。その季節感を感じられるのも、秋 なら
ではの魅力です。
□■ 秋の行事とコラボ ■□
さらに、秋の食材は、月見やお月見団子などの行事とも密接に関わっています。
例えば、十五夜の月見の定番グルメは、お月見団子。丸い形が満月を表すこの和菓子
には、栗が良く合います。また、ほっくりとした食感がホッと心に沁みわたるでしょ
う。
また、十日夜(11月10日)の「三月見」の際にも、松茸や栗を使った行事食が登場しま
す。自然の移ろいを感じながら、温かな団らんの時間を過ごせるのが魅力ですね。
このように、秋の食材は単に美味しいだけでなく、日本の伝統行事とも深くつながっ
ているのが特徴。季節を感じながら、心にも響く食の体験ができるでしょう。
□■ 秋の味覚を堪能しよう ■□
美しい紅葉、涼しい気候、そして何よりも美味しい季節の食材。まさに秋は至福の時
期といえます。
11月の食卓には、松茸やサンマ、栗など、秋ならではの味覚がそろっています。そん
な旬の恵みをたっぷりと味わい尽くしてみませんか?
温かな料理を囲んで家族や友人と楽しむのも素敵ですし、一人でゆっくりと味わうの
もいいかもしれません。秋の夜長、心も体も満たされる至福のひとときを過ごしてく
ださいね。
みなさん、こんにちは!
秋の気配が感じられる季節となってきましたね。そろそろハロウィンの飾り付けやイ
ベントの告知を目にする機会が増えてきました。街がオレンジ色に染まり始める10
月、今回はハロウィンについてお話ししていきたいと思います。
1.ハロウィンって何?古くて新しいお祭り!
ハロウィンの起源は、古代ケルト人のお祭り「サウィン祭」にさかのぼります。夏の
終わりを告げ、冬の始まりを祝う収穫祭だったんです。やがてキリスト教の影響を受
けて、現代のような形になっていきました。「Trick or Treat(お菓子をくれないと
いたずらするぞ)」という言葉、実は子どもたちが仮装して近所を回るという習慣
は、1930年代にアメリカで定着したものなんですよ!
2.日本のハロウィン、独自の進化!
日本でハロウィンが広く知られるようになったのは、実はそれほど古いことではあり
ません。1990年代後半から、テーマパークでのイベントとして少しずつ浸透し始めま
した。そこから、独自の発展を遂げていったんです。
日本のハロウィンの特徴といえば、なんといっても「仮装を楽しむ」という点!欧米
では子どもたちのイベントという側面が強いのですが、日本では大人も参加する一大
イベントに成長しました。渋谷や六本木といった繁華街は、毎年10月31日になると
様々なコスチュームに身を包んだ人々で埋め尽くされます。
3.ハロウィンはSNS時代の申し子!?
スマートフォンの普及とSNSの発展も、日本のハロウィン文化を大きく変えました。
インスタ映えする仮装や、ハロウィン限定スイーツ、さらにはペット用のコスチュー
ムまで!写真を撮って共有する楽しみが加わり、新しいコミュニケーションの形とし
て定着しています。
4.日本らしさ全開!ハロウィンフード
カボチャのお化けで有名なハロウィンですが、日本では食べ物でも独自の進化を遂げ
ています。オレンジ色や黒を基調としたスイーツ、おばけやコウモリの形をしたハン
バーグ、ジャック・オ・ランタンをモチーフにしたお弁当など、見た目も楽しい日本
らしいアレンジが満載です\(^o^)/
おわりに
このように、ハロウィンは日本の文化と融合しながら、独自の発展を遂げてきまし
た。伝統的な要素を残しつつも、現代的で楽しいお祭りとして進化を続けています。
今年のハロウィン、あなたはどんなふうに楽しみますか?
仮装をするもよし、スイーツを楽しむもよし、友人とパーティーを開くもよし。自分
らしい楽しみ方で、秋の夜長を彩ってくださいね!(*´▽`*)
みなさん、こんにちは!
9月1日は防災の日って知っていましたか?この日は1923年に起きた関東大震災にちなんで決められたんです。
最近、南海トラフ地震の臨時情報が出たり、大型台風が来たりと、自然災害のニュースを耳にすることが多いですよね。ちょっと怖いけど、しっかり備えておけば安心です!
というわけで今回は、家庭でできる防災対策についてお話しします。一緒に確認して、もしもの時に備えましょう!
1.非常用持ち出し袋、準備できてる?
まず大切なのが、非常用持ち出し袋の準備です。中身、何を入れればいいか悩みますよね。ここで、必需品リストをご紹介!
水と食料(3日分)
携帯ラジオと予備電池
懐中電灯
救急用品
常備薬
現金や身分証明書のコピー
使い捨てカイロ
マスクや消毒液
これらを、すぐに持ち出せる場所に置いておくのがポイントです。玄関近くのクローゼットとか、良いかも♪
2.家具の固定、やってある?
地震の時、倒れてくる家具が危険なんです。特に背の高い家具は要注意!タンスや本棚、冷蔵庫なんかは、転倒防止器具でしっかり固定しましょう。寝室や子供部屋の家具は特に大事ですよ。寝ている時に倒れてきたら大変ですからね
3.避難経路、家族で確認した?
いざという時、どこに逃げればいいか分かりますか?最寄りの避難所までの道順、家族みんなで確認しておきましょう。それと、複数のルートを知っておくのも大切です。道が塞がれていることもあるかもしれませんからね。
4.家族との連絡方法、決めてある?
災害時は電話がつながりにくくなります。そんな時に便利なのが、災害用伝言ダイヤル(171)や災害用伝言板サービス。使い方を確認して、家族で共有しておきましょう。LINEやTwitterなどのSNSも活用できますよ。
5.ハザードマップ、チェックした?
自分の住んでいる地域の危険な場所、知っていますか?市役所や町役場のウェブサイトで、ハザードマップが公開されていることが多いんです。洪水や土砂災害のリスクがある地域かどうか、チェックしてみましょう。知っているのと知らないのとでは大違い!
6.防災訓練、やってみない?
年に1~2回くらい、家族で防災訓練をしてみるのはどうでしょう。避難経路の確認、消火器の使い方、非常食の調理など、実際にやってみると良いですよ。子どもと一緒にやれば、防災教育にもなりますね♪
7.備蓄品、ローリングストック法で管理しよう!
備蓄品の管理って、けっこう面倒くさいですよね。そこでおすすめなのが「ローリングストック法」です。普段から少し多めに食料を買っておいて、古いものから使っていく方法です。使った分を補充すれば、いつも新鮮な備蓄品が保てますよ。便利でしょ♪
防災対策、一度にすべてやろうとすると大変ですよね。でも、少しずつでも始めることが大切なんです。今日から、できることからはじめてみましょう。
家族で話し合って、定期的に見直すのもいいですね。自然災害は避けられないかもしれませんが、準備をしっかりしておけば、被害を最小限に抑えることができます。
9月1日の防災の日を機に、みなさんも我が家の防災対策を見直してみてくださいね。家族の安全が一番大切ですからね!
それでは、安全で楽しい毎日を過ごしてください(^_^)v